中学生のお子さんを持つお母さん、「テスト勉強って、いつから始めさせればいいの?」「どうすれば効率よく点数が上がるの?」と悩んだことはありませんか?
この記事では、わが家の娘が塾に通わず、通信教育と家庭学習だけで3年間学年1位&オール5を達成した実体験をもとに、
・テスト2週間前からの具体的な勉強スケジュール
・ついやりがちなNG勉強法
・教科別の得点アップのコツ
などをわかりやすく紹介しています。
読んでいただければ、きっとお子さんに合った効果的な勉強の進め方や、親としてのサポートのヒントが見つかるはずです。
中学生のテスト勉強はいつ始める?効果的なのは「2週間前」から!
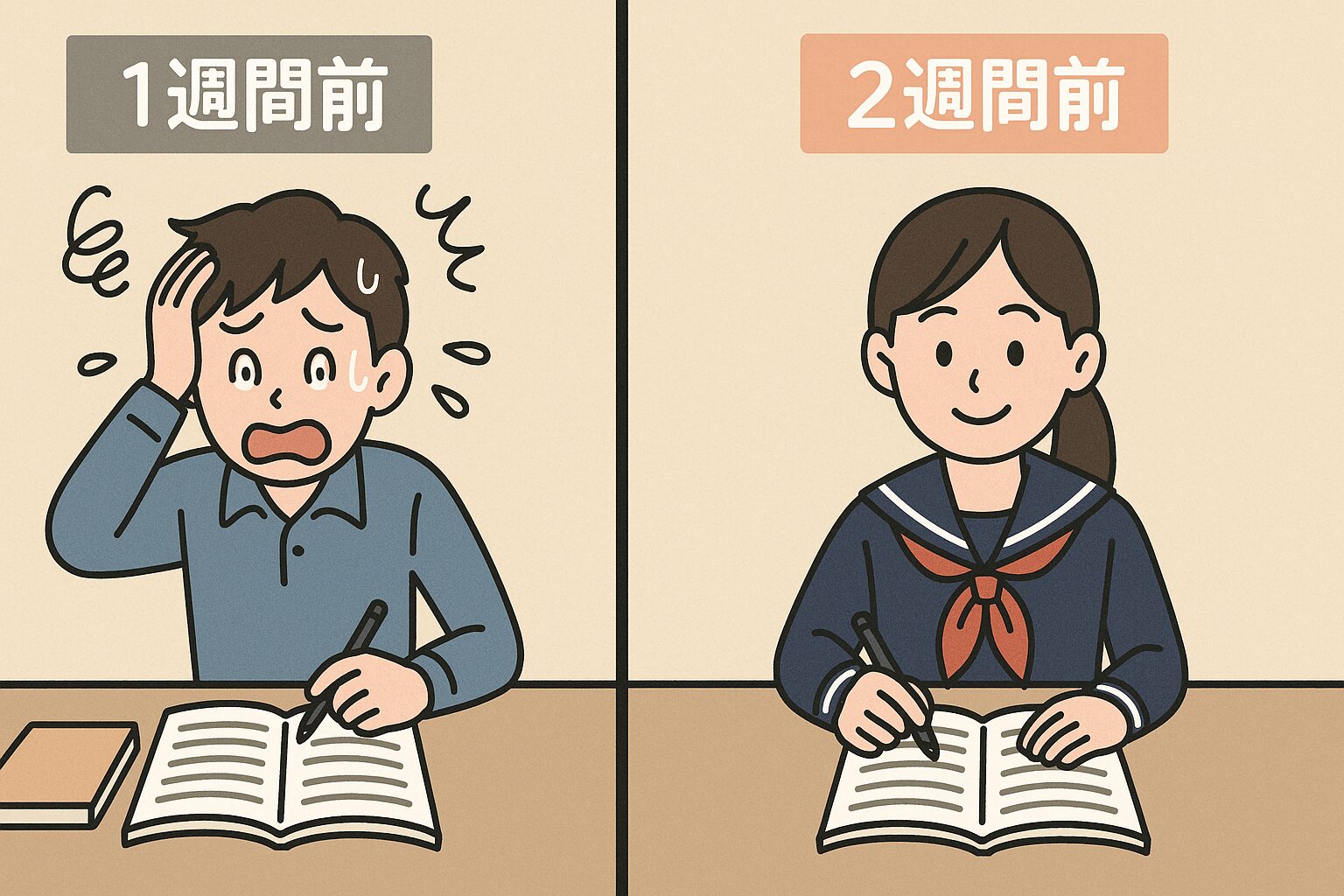
多くのお子さんがテスト1週間前、部活動が停止になってから本格的に始めますが、親としてはそれでは手遅れになるのではと心配になりますよね。中学校のテストは範囲が広く、科目数も多いため、直前の詰め込みでは知識が定着しにくいというのが、子どもを見ていて実感したことです。
実際に、中学生のテスト勉強時間の平均は1日2〜3時間とされていますが、これを1週間続けても総勉強時間は約20時間です。5教科すべてをカバーするには、親から見ても決して十分とは言えません。
2週間前から始めるメリット
①苦手科目の克服
早くから取り組むことで、苦手な分野にじっくり時間をかけることができます。うちの子も特に数学の計算問題や英語の文法理解など、積み重ねが必要な分野では、この余裕が大きな差を生んでいました。
②精神的な余裕
計画的に進めることで、「勉強が終わらないかも」という焦りがなくなり、テスト本番も落ち着いて臨めます。子どもを見ていても、この安心感があったからこそ、テスト中に冷静に問題を解くことができていたと感じています。
③知識の定着
繰り返し学習する時間を確保できるため、付け焼き刃ではない、本当に身につく学力が養われます。記憶は繰り返すことで長期記憶として定着するため、2週間という期間は理想的な学習スパンです。子どもの成長を見守る中で、これを実感することができました。
学年1位が実践!中学生の成績が上がる7つの鉄則
漠然と勉強を始めるのではなく、正しい手順を踏むことが高得点への近道です。ここでは、うちの子が実践していた7つのステップをご紹介いたします。親としてどのようにサポートしたかも含めてお伝えします。
ステップ1:テスト範囲を正確に把握して計画を立てる

まず、テスト範囲表が配られたら、科目ごとに「知っていること」と「知らないこと」を仕分けし、勉強の優先順位を決めるよう促しました。
具体的な計画の立て方として、うちの子は以下のような手順で進めていました。
- 全科目の範囲を一覧表にまとめる
- 各科目の理解度を3段階(◯完璧・△不安・✕全然わからない)で評価
- 「✕」の分野を最優先、「△」を次優先として時間配分を決める
- 目標点数を設定し、そこから逆算して日割りの学習計画を作成
この時点で親として大切にしていたのは、完璧を目指しすぎないことです。80点を目指すなら、80点分の内容を確実に押さえることに集中させていました。
計画表に沿って進めるには、教材の構成が分かりやすいものが◎。スマイルゼミなら、毎日のやることが画面に表示されるので計画が立てやすいです。
◆スマイルゼミ◆中学生向け通信教育ステップ2:基礎固めを徹底する(~10日前)
最初の数日間は、教科書と授業中のノートを徹底的に見直し、基礎知識を整理するよう声をかけていました。特に、先生が授業で強調していたポイントは出題される可能性が高いので、授業の様子を聞きながら一緒にチェックしています。
うちの子が実践していた基礎固めの方法:
教科書の活用法
- 太字部分や重要語句にマーカーを引く
- 章末問題を必ず解く
- 分からない部分は付箋を貼って後で質問する
ノートの見直し
- 授業中に先生が「ここは大事」と言った部分を再確認
- 板書以外に先生が口頭で説明した内容もチェック
- 友達のノートと比較して抜けている部分がないか確認
ステップ3:暗記科目は早めに手をつけて繰り返す
英単語、漢字、理科・社会の用語などの単純な暗記ものは、早くから始めるのが鉄則だと、子どもの様子を見ていて感じています。
効果的な暗記方法
まとめノートの作成も有効ですが、時間をかけすぎず、要点を絞って作成するよう見守っていました。うちの子の場合、A4用紙1枚に1科目の重要事項をまとめ、通学中などのスキマ時間に何度も見返しています。
暗記のコツとして、以下の方法を組み合わせて使うよう提案していました:
- 視覚的記憶:色分けや図表を活用
- 聴覚的記憶:声に出して読む
- 体感的記憶:手で書きながら覚える
特に効果的だったのは、寝る前の30分間を暗記時間に充てることです。睡眠中に記憶が整理されるため、翌朝の定着率が格段に上がることを、子どもの様子を見て実感しました。
ステップ4:ワークや問題集でアウトプット(~3日前)
基礎が固まったら、学校で配られたワークや問題集を解き始めるよう促していました。重要なのは「3回繰り返す」ことだと、子どもに伝えています。
3回繰り返し法の詳細
1回目:まずは何も見ずに解き、「完璧にできた(◯)」「間違えた(✕)」「自信がない(△)」を問題番号に直接書き込むよう指導しました。この時点では正答率を気にする必要はないと励ましています。現在の理解度を把握することが目的だからです。
2回目:「✕」と「△」の問題だけを解き直すよう促しました。解答を見て理解した後、必ず何も見ずに再度解いてみるよう見守っています。ただ答えを覚えるのではなく、解法を理解することが重要だと伝えていました。
3回目:再び、間違えた問題だけを解くよう指導しました。この段階で正解できない問題は、本当に理解が不足している部分なので、教科書に戻って基礎から確認するよう一緒に取り組んでいます。
この方法で、子どもが本当に理解していない部分だけを効率的に潰していくことができました。
ステップ5:苦手分野の最終チェック(前日~2日前)
テスト直前期は、新しいことに手を出すのではなく、今まで間違えた問題の最終確認に集中するよう声をかけていました。
この段階では、「完璧にできる問題」「時間をかければできる問題」「どうしてもできない問題」に分類し、2つ目のグループに重点を置くよう助言しています。最後のグループは思い切って捨てる勇気も必要だと、親として伝えていました。
特に苦手な問題は、何度も繰り返し解き、解法を体に覚え込ませるよう見守っていました。うちの子は、苦手な数学の問題を20回以上解いたこともあります。そこまでやると、問題を見ただけで解法が浮かぶようになることを、親として間近で見ていて実感できました。
ステップ6:集中できる環境を整える
勉強する場所は、静かで集中できる環境が理想です。親としてうちで実践していた環境づくりのポイント:
物理的環境
- 机の上には必要な教材だけを置くよう声をかける
- 適度な明るさ(目が疲れない程度)を確保
- 室温は少し涼しめ(22〜24度程度)に設定
デジタル環境の整備
- スマートフォンは電源を切って別の部屋に置くよう促す
- パソコンは勉強以外のサイトをブロック
- 音楽は歌詞のないものに限定(集中力が散漫になるため)
時間管理
- 50分勉強+10分休憩のサイクルを基本とするよう提案
- 長時間同じ科目を続けず、適度に科目を切り替えるよう見守る
ステップ7:テスト直前の総復習
前日は、暗記科目の最終チェックと、これまでの復習で使ったノートや問題集全体にざっと目を通す程度にするよう見守っていました。
うちの子の前日の過ごし方:
- 朝:軽い復習(1時間程度)
- 昼:普通に過ごす
- 夕方:暗記事項の最終確認(30分程度)
- 夜:早めに就寝(23時まで)
十分な睡眠をとり、万全の体調で本番に臨むことが何よりも大切です。睡眠不足は判断力を大きく低下させ、せっかく覚えた内容も思い出せなくなります。親としては、このリスクを忘れずに睡眠の重要性を伝えるよう心がけています。
娘はテスト前日は、23時までに必ず寝るようにしています。一度だけ24時を超えてしまったときがありましたが、計算ミスをするなど実力が発揮できなかったようです。
【教科別】中学生が高得点を狙うための重要ポイント
国語
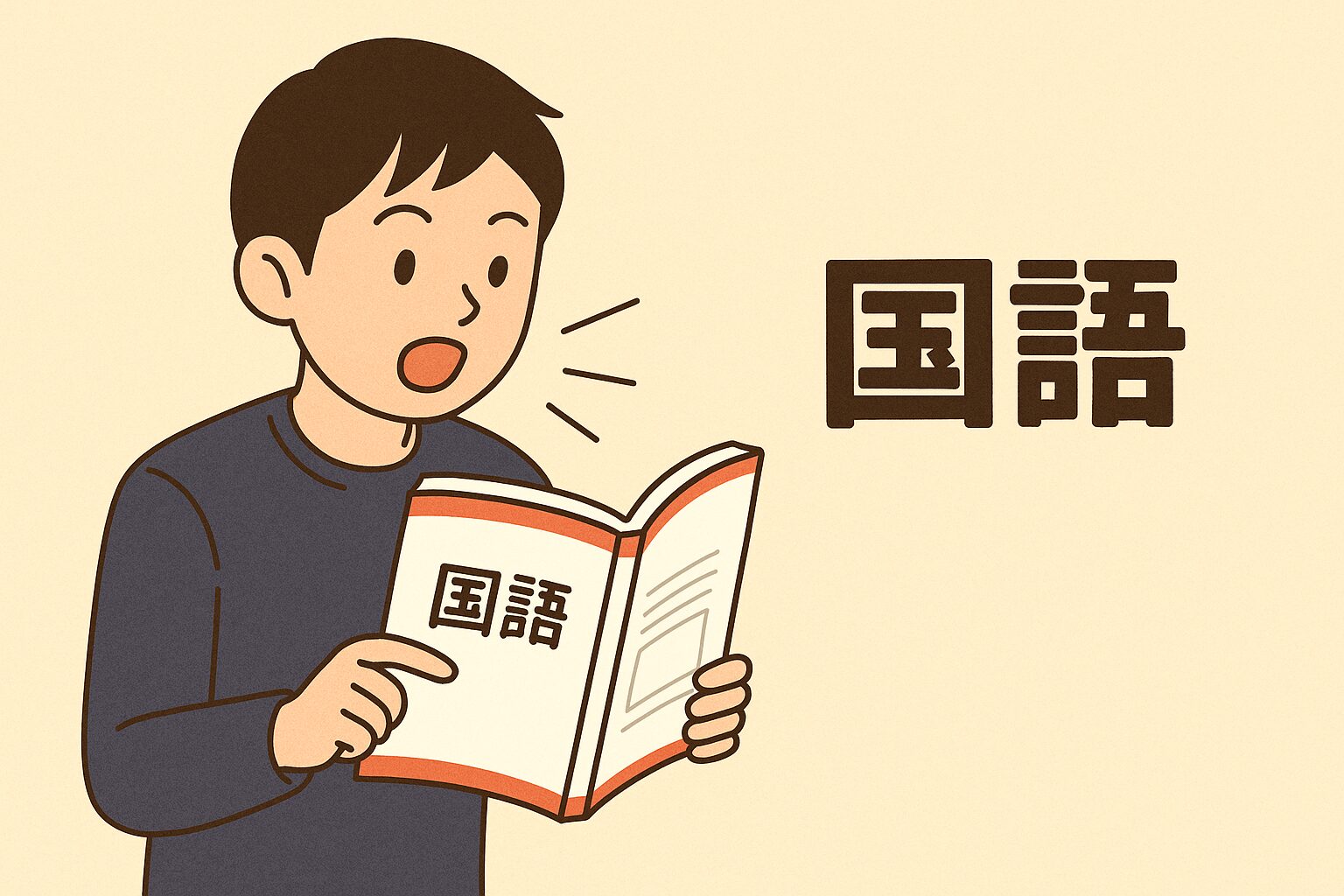
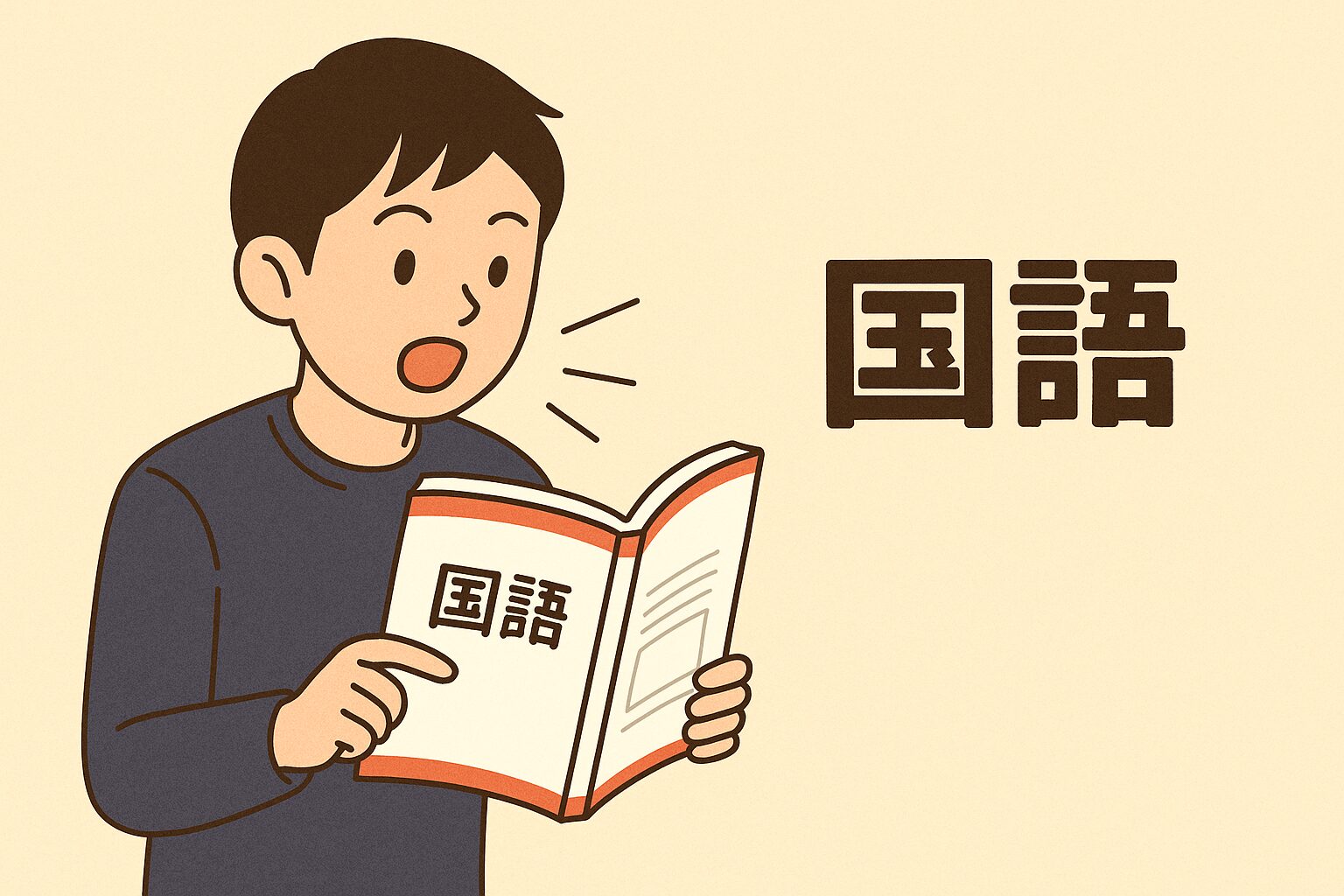
漢字・文法・語句
これらは暗記すれば必ず点になる部分です。最優先で完璧にするよう子どもに伝えていました。特に漢字は、「読み」だけでなく「書き」も含めて練習することが重要だと感じています。
読解問題
授業で扱った文章の内容をしっかり理解しておくことが重要です。先生が説明したポイントや接続詞(しかし、つまり、など)に注意して、教科書を音読するよう促していました。
- 教科書の文章を最低3回は音読する
- 重要な表現技法(比喩、擬人法など)を覚える
- 作者の背景や作品の時代背景を理解する
数学
公式の理解
公式を丸暗記するだけでなく、「なぜこの公式を使うのか」を理解することが大切だと子どもに説明していました。公式の導出過程も含めて理解すると、応用問題にも対応できることを実感しています。
計算力の強化
ワークの問題を繰り返し解き、計算ミスをなくし、スピードを上げるよう見守っていました。応用問題が解けなくても、途中式で部分点がもらえることもあると励ましています。
- 基本的な計算問題を確実にマスター
- 典型的な解法パターンを覚える
- 応用問題は解法の組み合わせとして理解
- 計算ミスを防ぐため、見直しの習慣をつける
英語
単語・熟語
テスト範囲の単語・熟語は完璧に暗記するよう促していました。これが全ての基本だと感じています。単語を覚える際は、スペル、意味、発音の3つをセットで覚えることが重要だと子どもに伝えていました。
基本文法
教科書の例文をそのまま覚えるくらい、何度も音読し、文の構造を理解するよう見守っていました。文法は理屈で理解し、例文で感覚を身につけるという両方のアプローチが効果的だと実感しています。
長文読解
授業で扱った長文は、スラスラ和訳できるまで読み込むことが高得点への鍵だと子どもに伝えていました。分からない単語があっても、文脈から推測する力も身につけるよう励ましています。
- 毎日必ず英語に触れる(継続性が重要)
- 音読を必ず取り入れる(発音と意味を結びつける)
- 英文を書く練習も忘れずに行う
理科
用語の暗記
図や表と関連付けて、用語の意味を正確に覚えるよう指導していました。単純な暗記ではなく、現象と用語を結びつけて理解することが大切だと感じています。
実験問題
「実験の目的・手順・結果・考察」の4点をセットで理解することが重要だと子どもに説明していました。なぜその実験を行うのか、どのような結果が期待されるのかまで理解できるよう見守っています。
- 教科書の図表を使って視覚的に理解
- 実験のポイントを自分の言葉で説明できるようにする
- 計算問題は公式の使い方をパターン化して覚える
社会
流れの理解
単純な人名や年号の暗記だけでなく、「なぜそうなったのか」という出来事の背景や因果関係をストーリーとして理解することが大切だと子どもに伝えていました。
- 地理:地図を活用し、位置関係と特徴を関連付ける
- 歴史:時系列を意識し、原因と結果の関係を理解
- 公民:現代社会との関連を考えながら学習
教科書をじっくり読み込み、ノートに要約するのも効果的です。ただし、要約に時間をかけすぎず、理解することに重点を置くよう見守っていました。
要注意!成績が伸びない中学生のNG勉強法4つ
多くの中学生が陥りがちな、効果の低い勉強法を紹介します。思い当たるものがあれば、親としてそっと声をかけてあげてくださいね。
①とりあえずワークを最初からやる
自分の理解度に関係なく1ページ目から始めるのは非効率です。まずは全体を見渡し、苦手な単元から優先的に取り組むよう促しましょう。できる問題に時間をかけるより、できない問題を潰す方が得点アップに直結することを、子どもと一緒に確認していました。
②夜型の詰め込み勉強
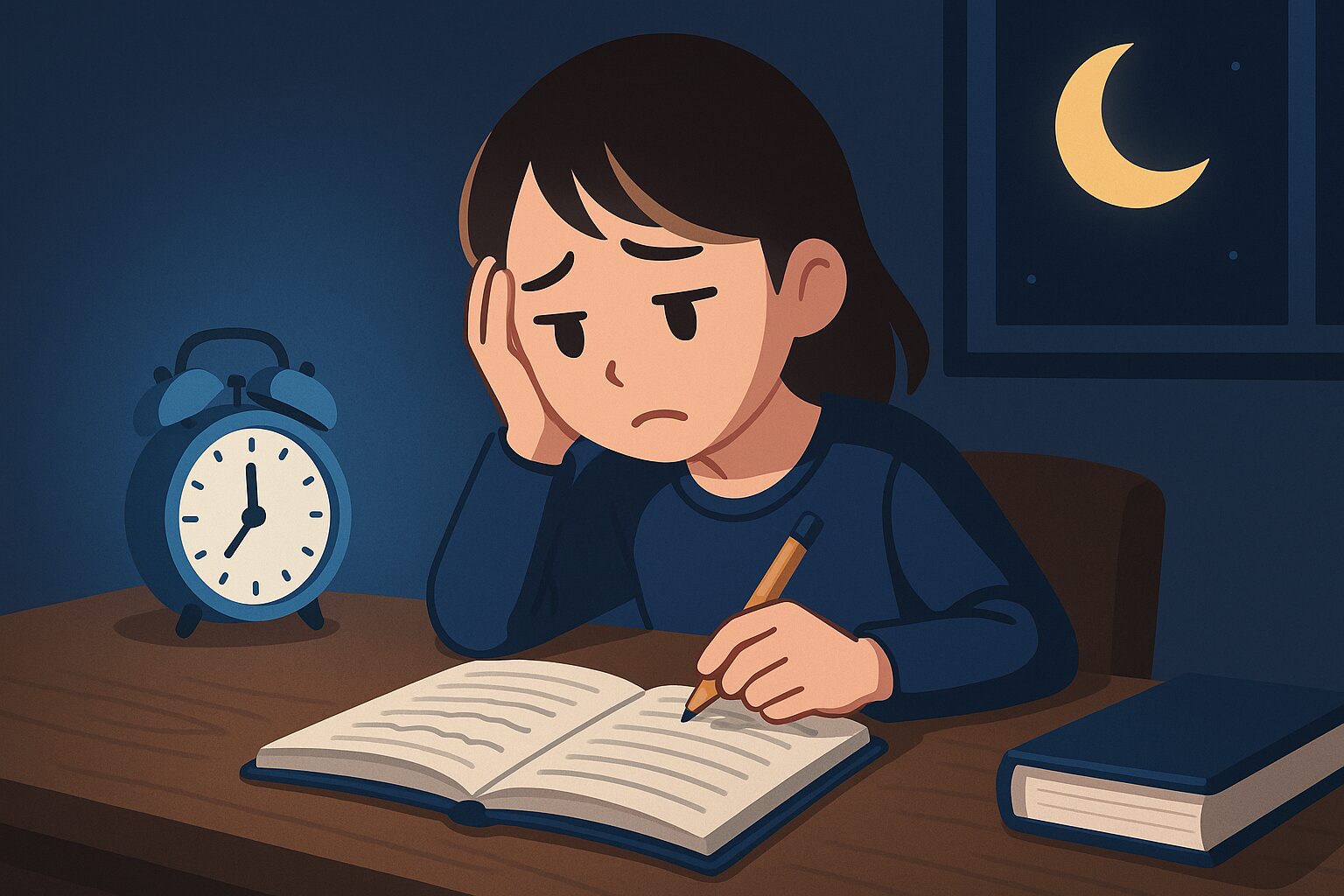
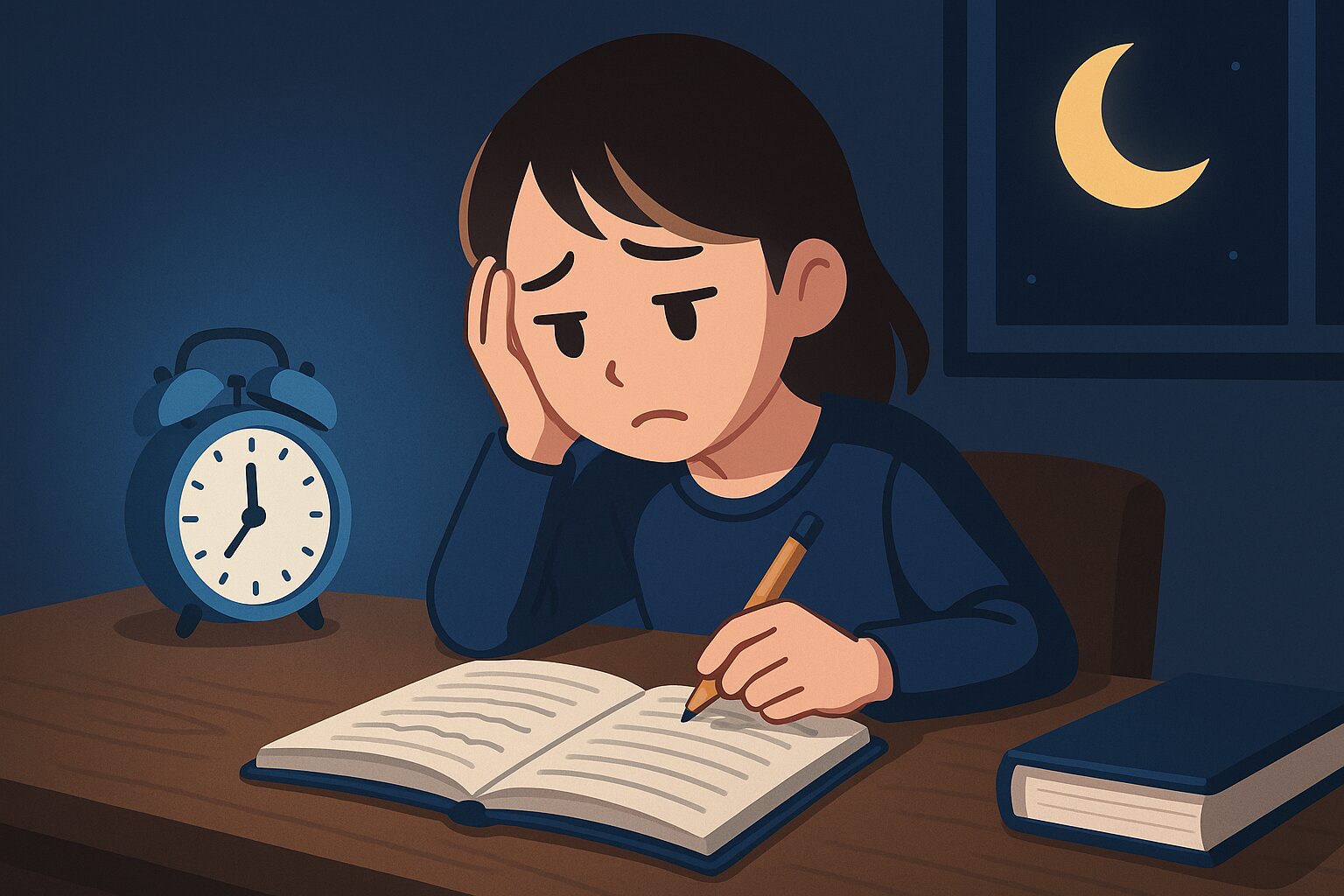
睡眠不足は記憶の定着を妨げ、集中力を低下させます。テスト前こそ、規則正しい生活を心がけ、十分な睡眠時間を確保するよう親として見守ることが大切です。理想的な睡眠時間は7〜8時間です。
③きれいなノート作りに満足する
ノート作りが目的になってしまい、肝心な内容が頭に入っていないケースです。ノートはあくまで覚えるためのツールと考え、時間をかけすぎないよう子どもに伝えていました。美しさよりも実用性を重視することが大切だと感じています。
④友達と一緒の勉強に頼りすぎる
友達と一緒に勉強することで安心感を得られますが、おしゃべりに時間を取られがちです。基本的には一人で集中して勉強し、分からない部分を質問し合う程度に留めるのが効果的だと、子どもの様子を見ていて感じました。
塾なしで学年1位!家庭学習を成功させる秘訣
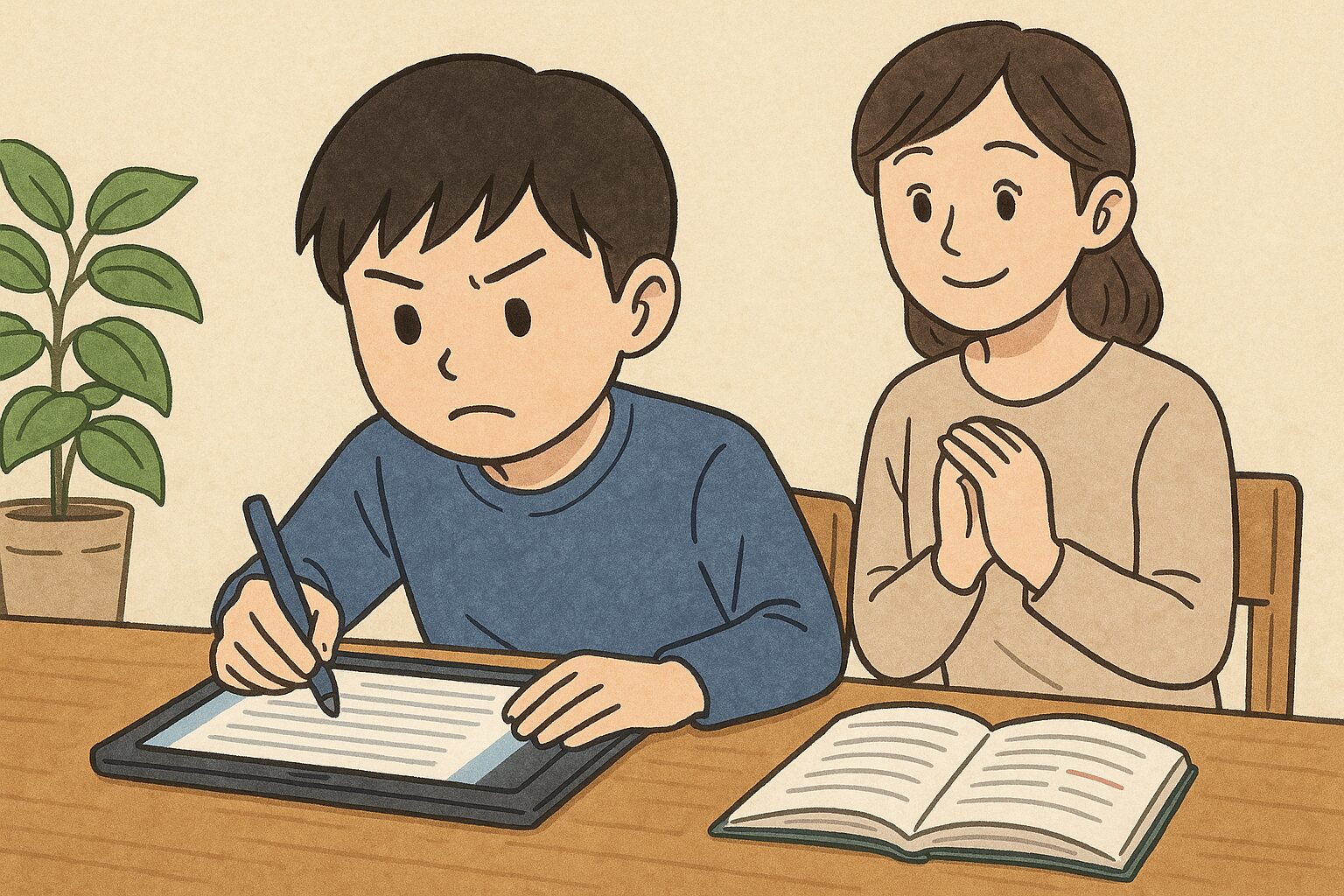
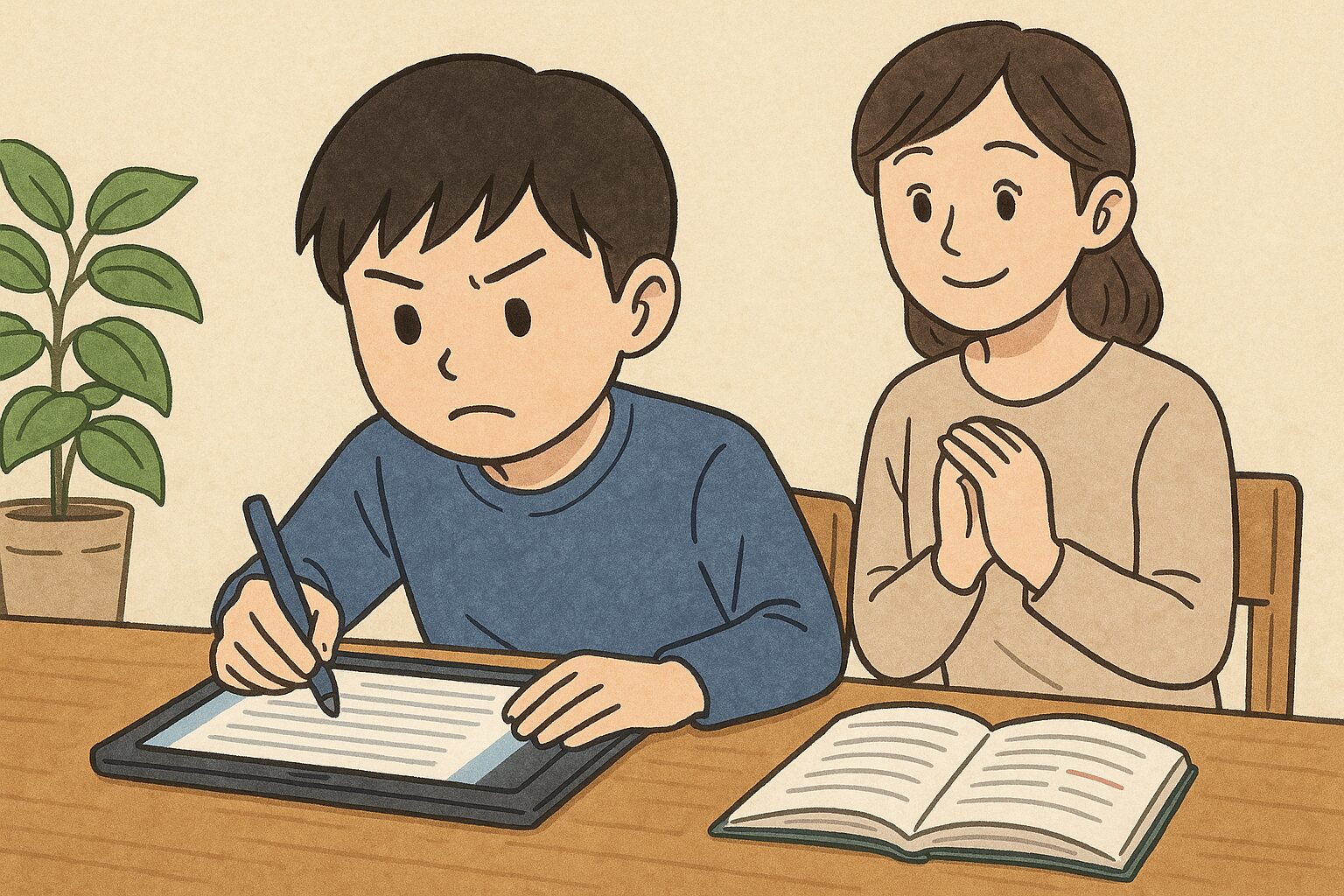
うちの子が塾に通わずトップの成績を維持できたのは、通信教育をうまく活用し、家庭での学習習慣を確立したからです。親としてどのようにサポートしたかをお伝えします。
通信教育の活用法
スマイルゼミや進研ゼミといった教材を使い、子どものペースで学習を進められるよう見守りました。教材を選ぶ際は、解説の分かりやすさや、子どものレベルに合っているかを重視しています。
通信教育を活用する際に親として心がけていたポイント
- 毎日決まった時間に取り組む習慣をつけるよう声をかける
- 分からない問題は放置せず、必ず解決するよう一緒に取り組む
- 定期的に理解度をチェックし、必要に応じて復習を促す


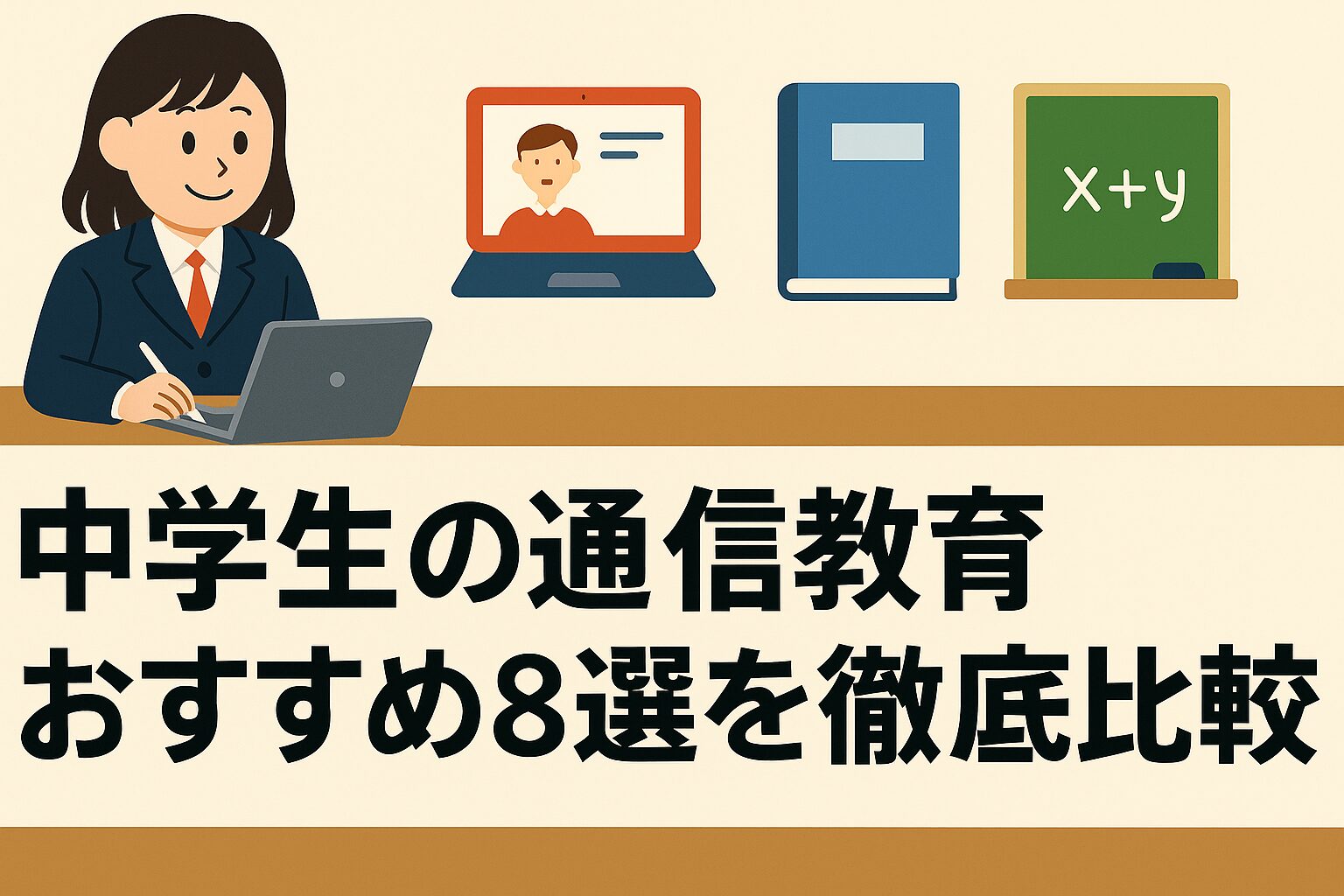
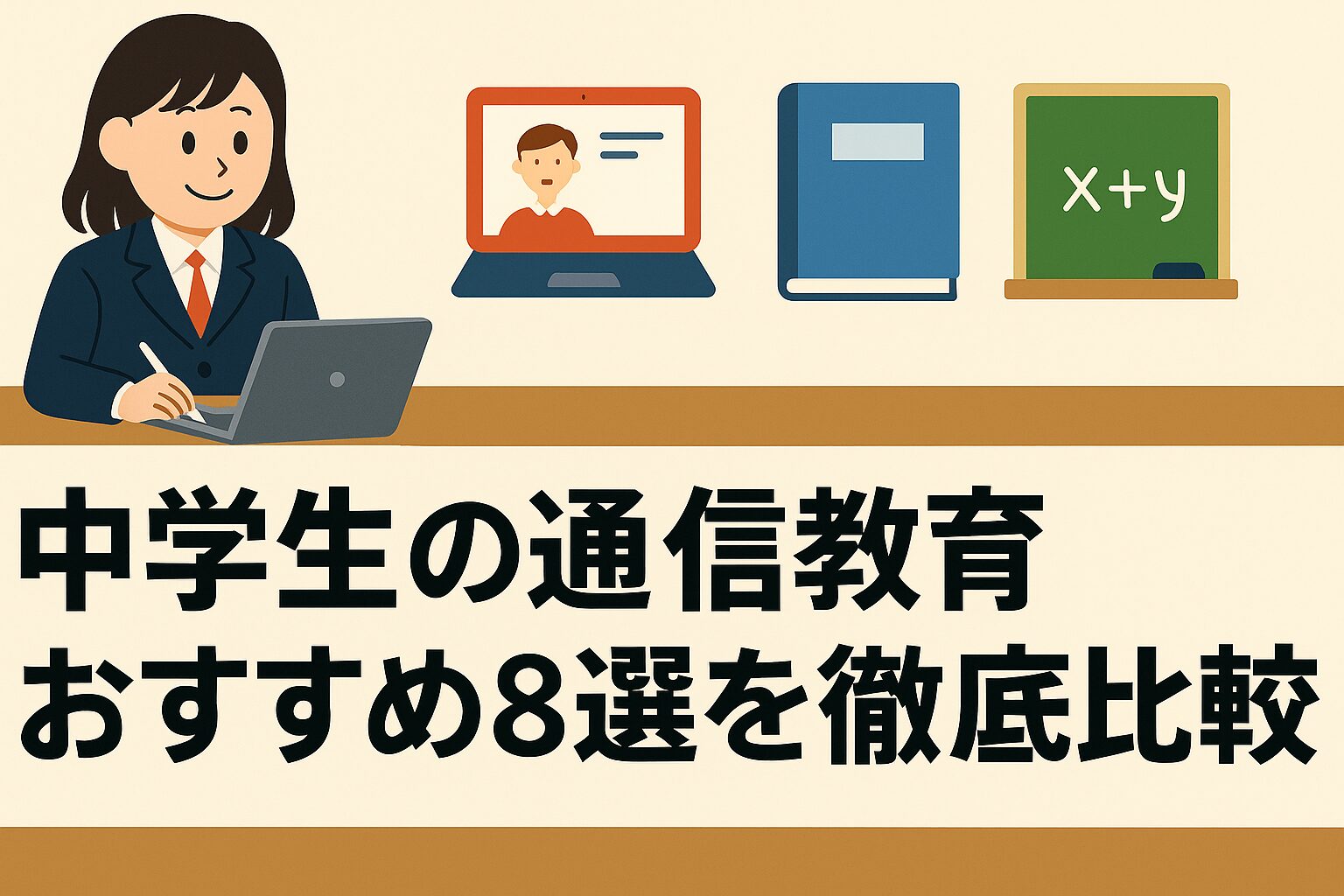
家庭学習の習慣化
「平日は毎日2時間」「休日は4時間」のように、勉強時間をルール化し、学習を生活の一部にするよう見守りました。
また、親として「勉強しなさい」と強制するのではなく、「この問題、面白いね」「昨日より進んだね」といった前向きな言葉で、やる気を引き出す工夫をしています。
- 子どもの勉強を監視するのではなく、サポートに徹する
- 結果だけでなく、努力のプロセスを評価する
- 適度な息抜きの時間も確保してあげる
- 勉強環境を整えることで間接的にサポートする
中学生のテスト成功の鍵は「早めの準備」と「正しい計画」


中学生のテスト勉強は、決して難しいものではありません。大切なのは、2週間前から計画的に始めること、そしてお子さんに合った正しい勉強法を見つけることです。
今回ご紹介した方法は、うちの子が3年間実践して効果を実感したものばかりです。しかし、すべての方法が全てのお子さんに合うわけではありません。まずは取り入れやすいものから始めて、お子さんなりにアレンジしていくことが重要だと感じています。
テスト勉強は短期的な成果だけでなく、将来の高校受験、そしてその先の人生にも活かせる学習習慣を身につける貴重な機会です。今回ご紹介した方法を参考に、親子で万全の態勢でテストに臨み、目標点数を達成してください。
お子さんの努力が必ず結果につながることを、同じ母親として心から願っています。一緒に頑張りましょう!


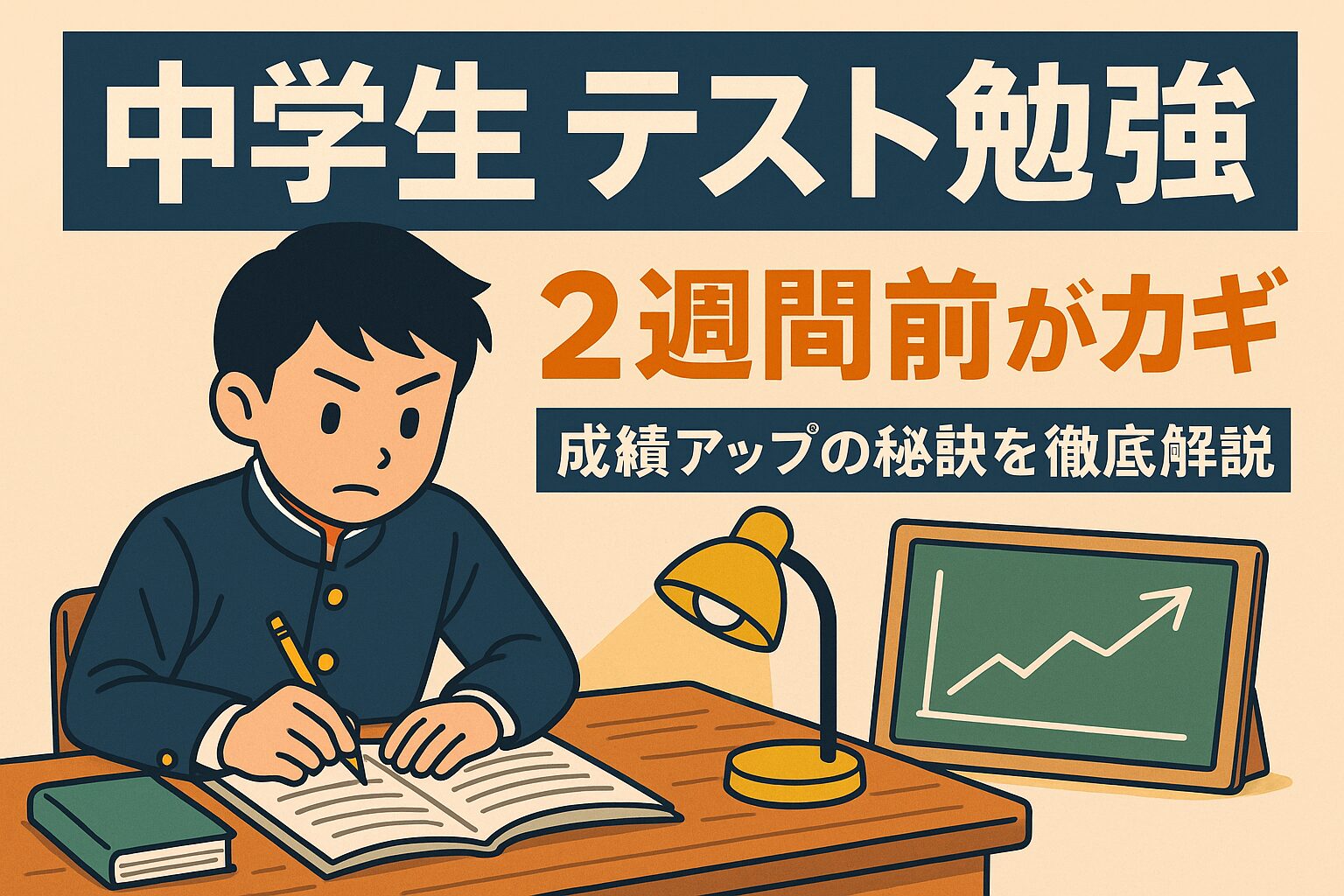
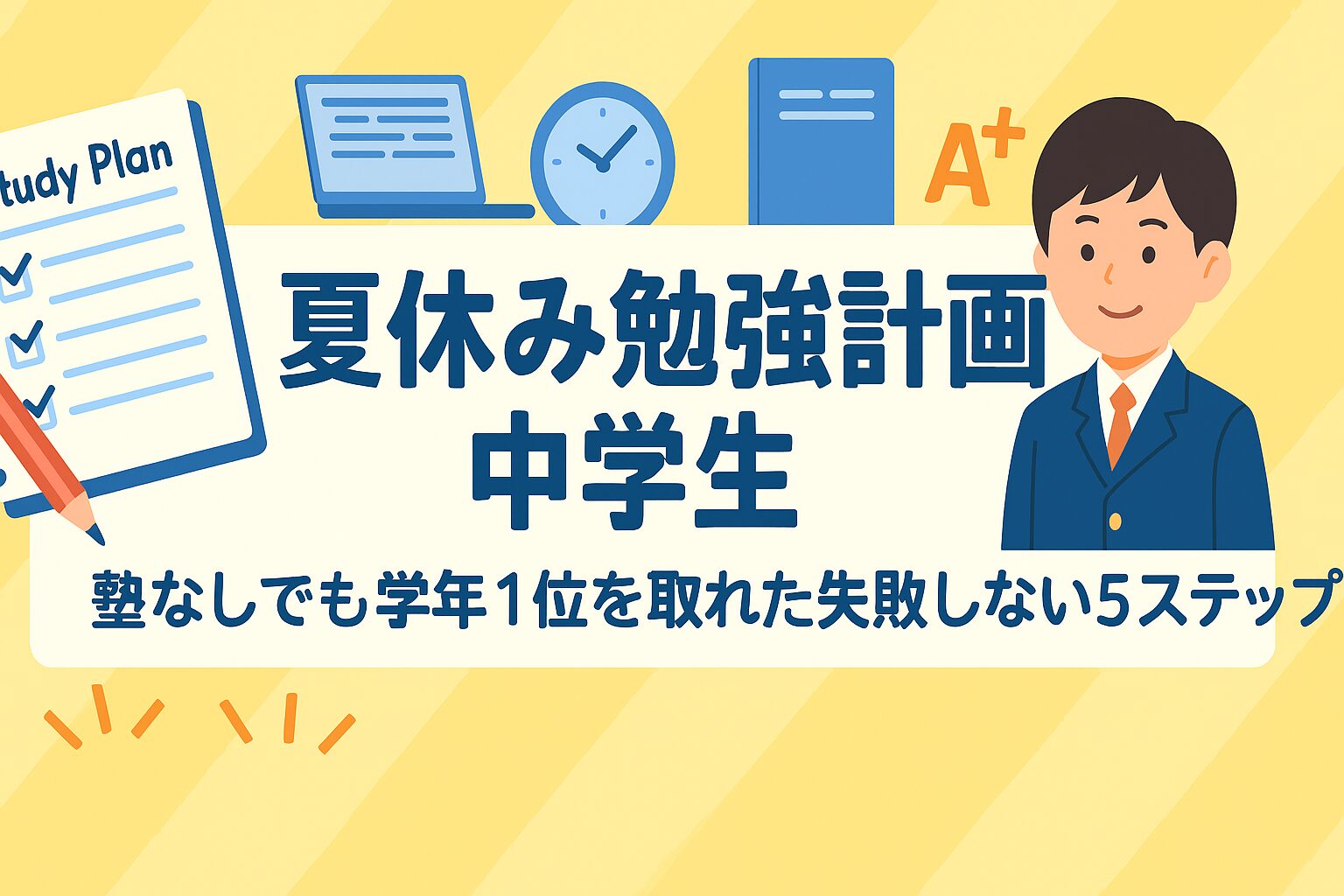
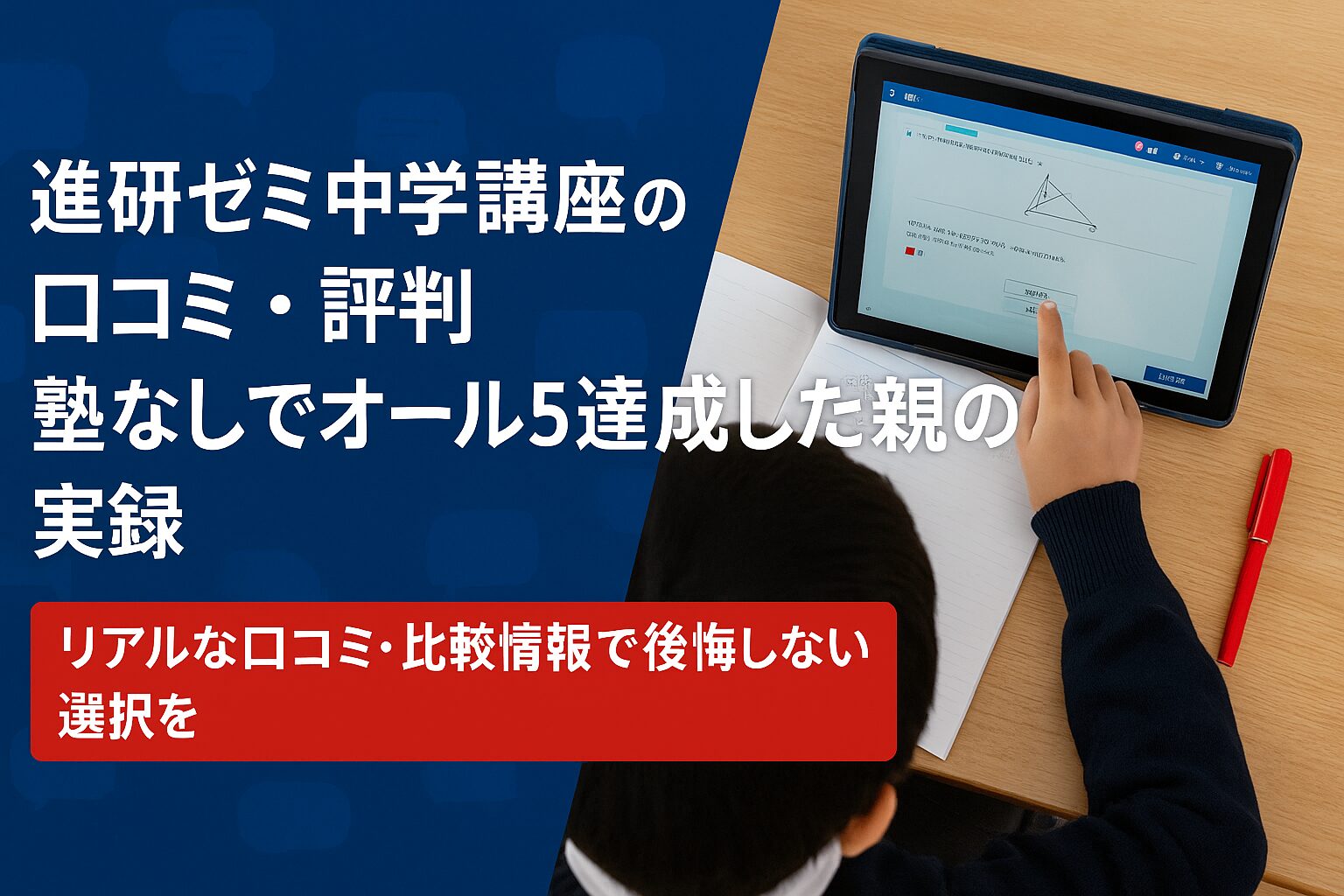
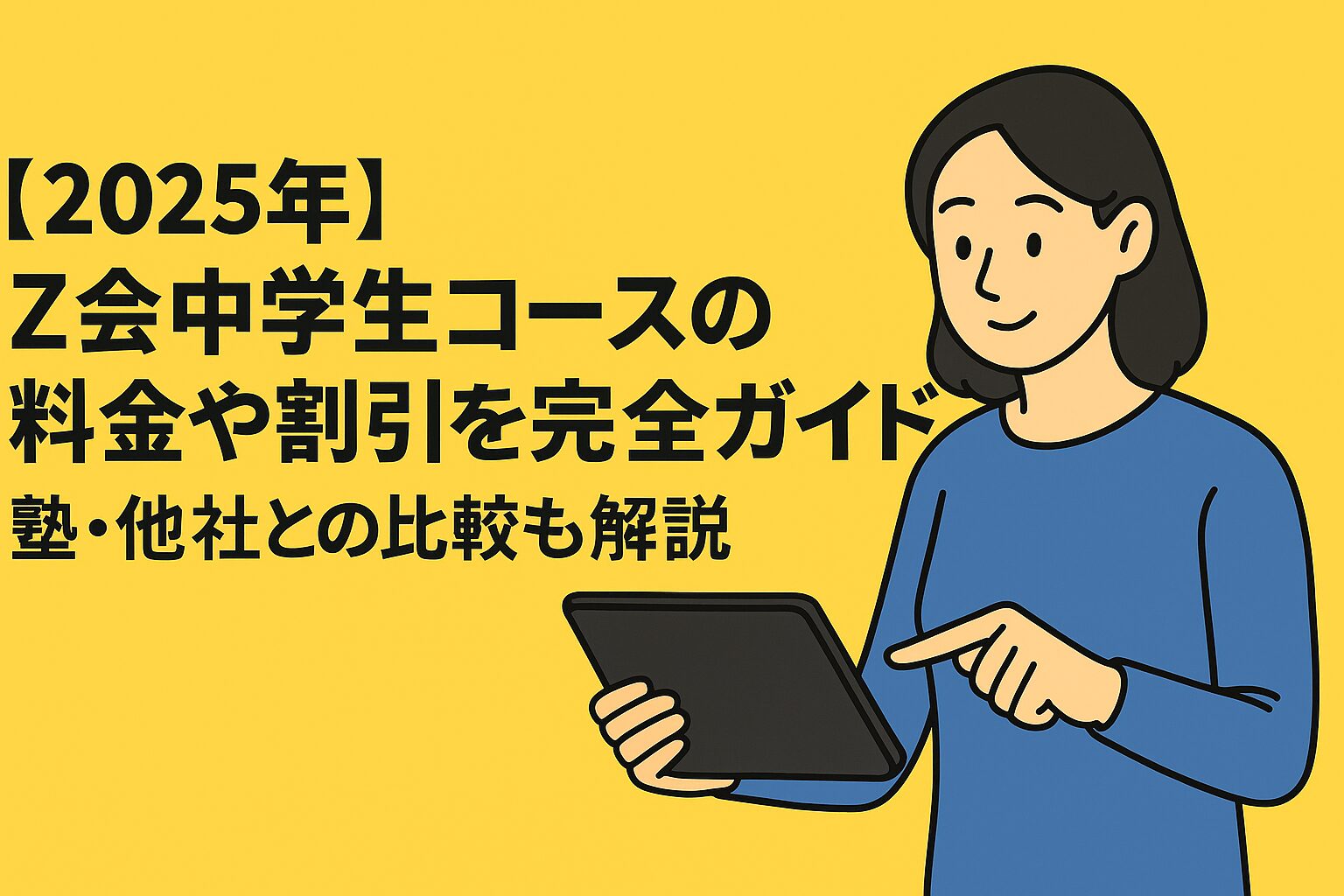
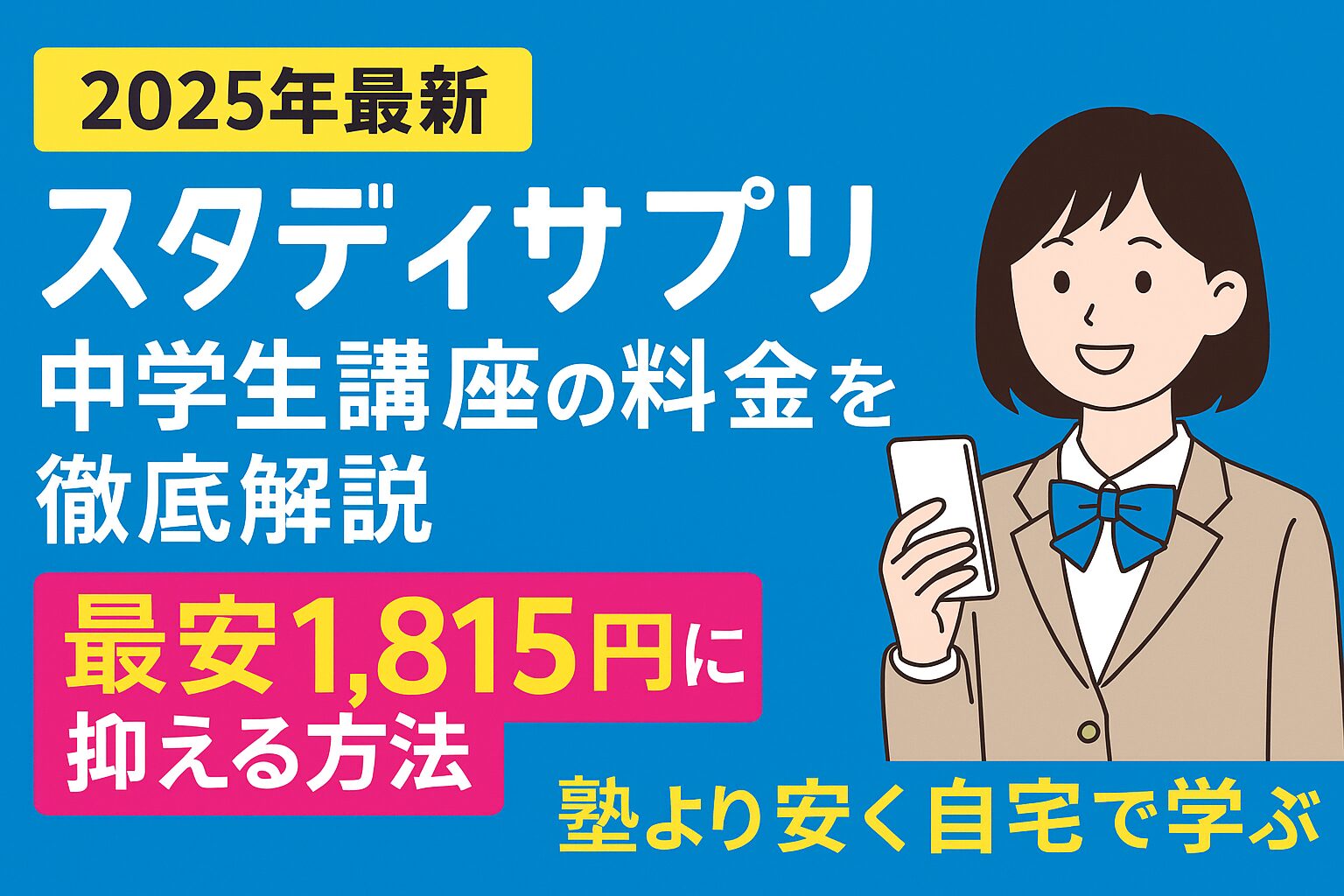
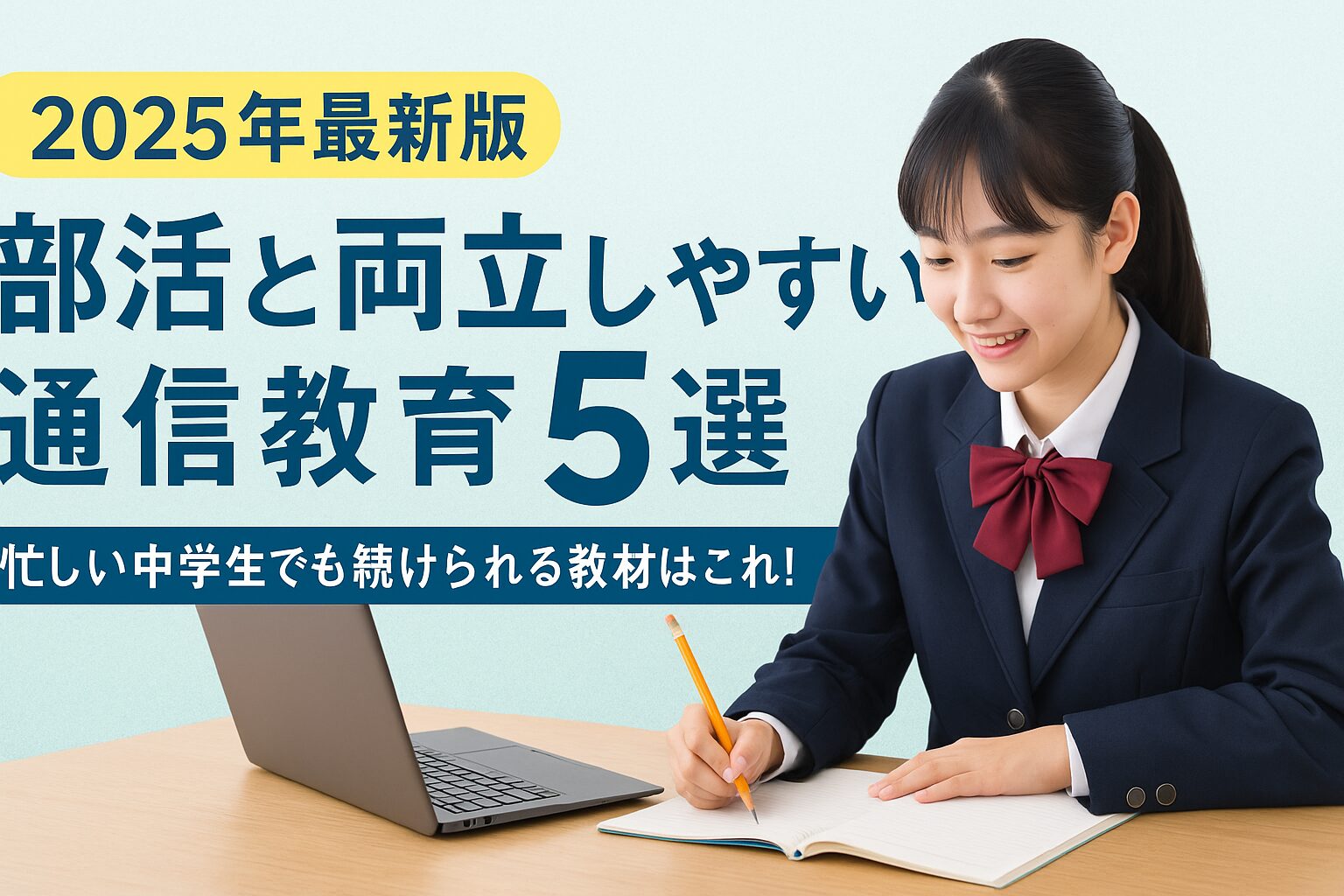
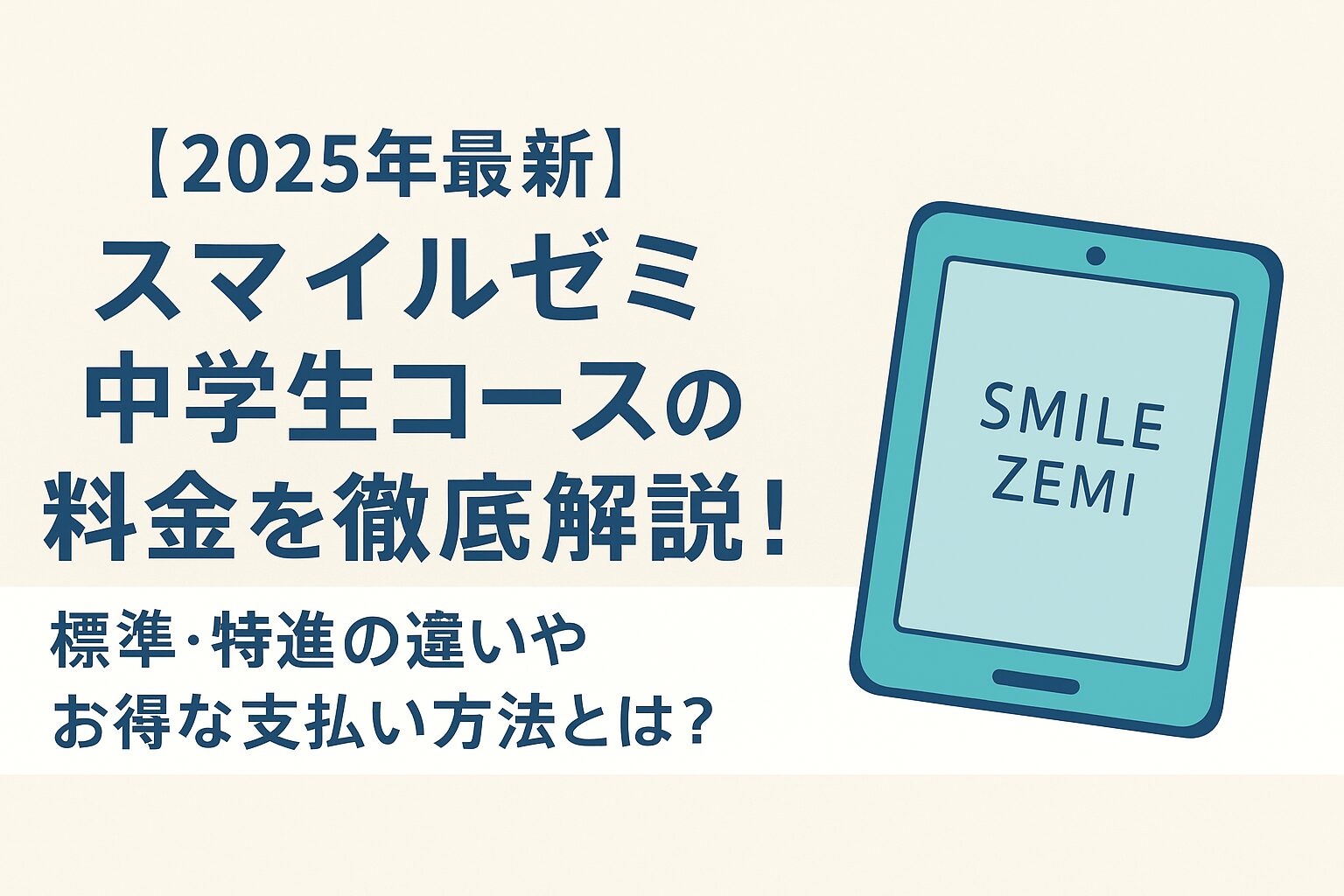
コメント